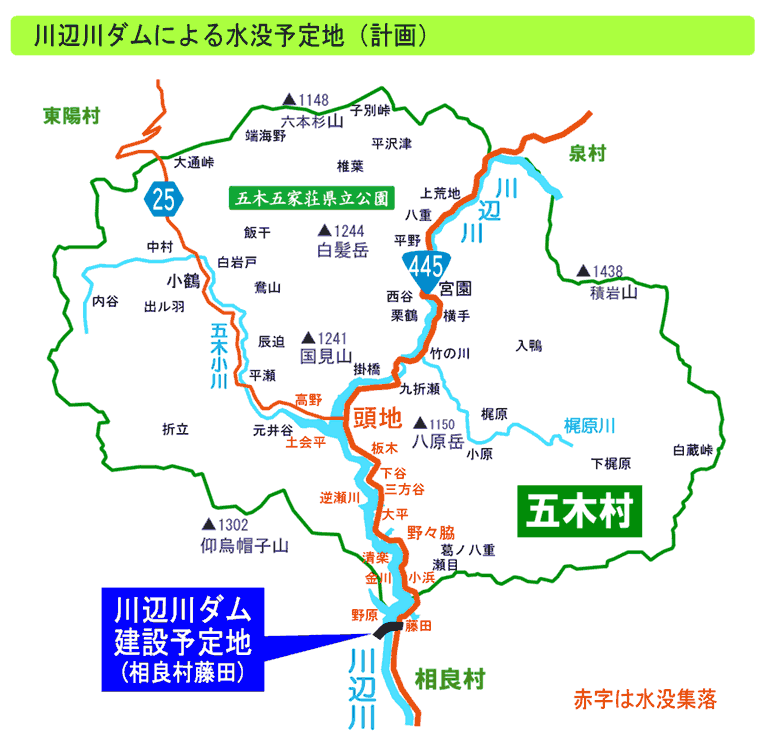|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
◆中級編 |
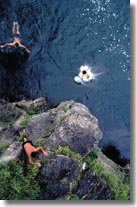 |
| ■1.川辺川ダムはどこに計画されているの? |
九州山麓に水源を持ち、不知火海へと注ぐ球磨川。球磨川は日本三大急流の一つとして知られ、全長115km、流域面積1880平方kmを持つ九州で第3位の大河です。
その最大の支流が川辺川です。支流とは言っても球磨川の流域の30%をしめる大きさで、長さ62kmになります。源流は八代市泉町で、平家の落ち人伝説の残る五家荘や、子守唄の里として知られる五木村を通り、相良村で本流の球磨川に合流します。
1998年、環境庁による水質調査で、川辺川の水は日本一の清流と認定(環境基準満足度上位水域ベスト1)されました。また、2006年以降2023年まで17年連続で、国交省の水質調査でも全国一位に認定(国交省の全国一級河川の水質調査「水質が最も良好な河川」)されています。清流は良質な鮎に代表される豊かな生態系を育み、「尺鮎」と呼ばれる全長30cm以上もの天然鮎の産地としても全国に知られています。
川辺川ダム建設予定地は、この川辺川の中流、熊本県球磨郡相良村の北部、藤田地区にあります。
| ■2.新旧の川辺川ダムの概要は? |
1966年に国土交通省九州地方整備局によって計画された川辺川ダム事業は、治水、利水(農業用水)、発電を目的とした多目的ダムでした。
ダム本体工事をのぞく関連工事が進む中、ダム本体の建設は未着工の状態が続いていましたが、1990年代半ば〜2000年初頭にかけて、市民による強い反対世論が高まり、球磨川流域を中心に県内や全国へと川辺川ダム計画の問題点が広く知られるようになりました。
その後、ダムから水を引く灌漑事業である国営川辺川土地改良事業は、農家同意を巡る裁判で2003年に農水省が敗訴し白紙に。その影響で国の強制収用手続きも2005年に手続きやり直しとなりました。2006年、農水省は正式に利水事業撤退、2007年に電源開発(株)も発電事業から撤退を表明。地元自治体首長の意向を受け、2008年には県知事が「球磨川は県民の宝」として県政史上初めてダム反対を表明。翌2009年には国も正式に中止を発表し、川辺川ダム計画は姿を消し、ダムによらない治水やダムと切り離した水没予定地の地域振興事業が進んでいました。
しかし、ダムによらない治水対策の協議は、国が実現不可能な代替案の提示を続け、各自治体首長も遊水地整備などに難色を示し、実質的にはダム代替案はほとんど進まないままに12年間が過ぎました。
そのような中で2020年7月、球磨川豪雨災害が発生しました。その後国交省と県は、災害の検証もそこそこに「命と環境を守る唯一の選択肢」として、治水のみを目的とした流水型(穴あき)ダムに計画を変更し、再び事業を再開しました。現在、住民説明や住民参加の機会を設けないままに、関連事業や環境アセスメント手続きなどが進められています。
旧川辺川ダム
新川辺川ダム(流水型)
位置
熊本県球磨相良村大字四浦字藤田(左岸)、堂迫(右岸)
同じ
ダムの形式
アーチ式コンクリートダム
重力式コンクリート、流水型
堤高
107.5m
ほぼ同じ(107mほど)
堤頂長
283m
ほぼ同じ(280mほど)
総貯水量
1億3300万立米
ほぼ同じ(1億3000万立米程度)
流域面積
3.91km2
同じ
湛水面積
3.91km2(391ha)
? ほぼ同じ
事業者
国土交通省
同じ
ダムの目的
- 洪水調節(治水)
- 発電(2007年に電源開発撤退)
- かんがい(2006年農水省撤退)
治水
着手
1967年
(従来のダム計画から継続)
完成予定
2008年
2035年
完成予想図

予算
2,650億円(1998年)としていたが、内部資料リークにより3,300億円と判明 ※当初は350億円
今後かかる費用が2,680億円で、
従来ダムと合計して 4,900億円費用対効果
(B/C)0.73
※国は1.55としていたが、住民側は0.73と指摘1967〜2035年 / 0.4
2022〜2035年/ 1.9
| ■3.従来の川辺川ダムの目的は何だったの? |
従来の川辺川ダムの目的は、洪水調節、流水の正常な機能の維持、農業用水の供給、発電とされていましたが、市民グループはそれぞれの目的はすでに破綻しており、ダム建設によって流域の生態系や住民の暮らしが大きな被害を受けると考えていました。
ダムの目的 国交省の説明資料より わたしたちの考え 1 洪水調節
(治水)梅雨や台風などで大雨が降ったときに、川辺川を流れる水の一部をダムに貯め川に流れる水を減らして人吉市や八代市などを氾濫から守ります。 かつての洪水の原因は、山の乱伐によって保水力が大きく失われていたことと、堤防の整備などの河川改修が遅れていたことが原因。現在、森林の保水力は回復に向かい、河川改修も進み、過去最大の洪水が来ても、一部の未改修地区を除けば球磨川からあふれることはない。さらに河道の整備を進めたり、間伐を進めるなど森林の手入れを行うことで、流域の総合的な治水対策は十分可能。 2 流水の正常な機能の維持 球磨川を流れる水量が少ないときにアユなどの河川に生息する動植物を守り、また、川下りが欠航しないようにダムから水を補給します。 「流水の正常な機能の維持」は、ダムより下流の川の水量を一定量以上確保することを指す。これは下流域の既得水利の保護と、ダム建設によって川が受けるダメージ緩和のための補償的な措置にほかならず、ダムを造る理由には当たらない。 3 農業用水の供給(利水) 人吉球磨地方の1市2町4村にまたがる球磨川右岸(相良村など)の農地は日頃から水が不足しがちです。この地区は、市房ダムから農業用水が供給されている球磨川左岸(免田町、多良木町など)に比べて農業基盤整備は著しく遅れており、川辺川ダムからこの地区へ農業用水を供給することにより、収穫の安定や品質の向上が図られ、生産性の向上や農業経営の安定化に寄与します。 計画が作られたのは戦後の食料増産期で、現在は水をそれほど必要としないお茶や牧草、果樹栽培への転作が進んでいる。
川辺川利水訴訟の農水省側の敗訴によって、利水事業への同意取得が違法な手続きによって進められたことが明らかになった。農業用水の必要な地域には、従来の水利施設の改修や、既存水源の利用による代替が十分可能。4 発電 川辺川ダムによる落差を利用し、最大出力16,500kwの電力を生み出します。このクリーンなエネルギーは、主として人吉球磨地方を中心とした南九州に供給されます。 ダム建設による水没で閉鎖される3つの発電所の最大発電量の合計は15,900kw。川辺川ダムによって発電される最大発電量は16,500kwで、その差はわずか600kw。川辺川ダムによる発電も補償的な措置にほかならず、ダムを造る理由には当たらない。 上記のうち、2の「流水の正常な機能の維持」は、全国の治水ダムで建設目的の1つとして便宜的にげられるものです。「ダムによって生態系が守られ、流量が適正に確保できる」とする作為的な目的に過ぎません。
3の「農業用水の供給(利水)」については、利水訴訟勝訴により、農水省の手続きに誤りがあったことが明らかになりました。利水事業(国営川辺川土地改良事業)の農家同意取得をめぐる手続きで、農水省が、不参加を表明した本人の意向を無視して事業に参加させたり、すでに亡くなっていた人の名前や本人のものではない印鑑を押印した同意書を偽造したりしていたことが、裁判で明らかになったのです。その後、国・県・自治体・利水訴訟原告農家が一体となって新利水計画の協議を重ねましたが、農家を巡る状況は大きく変化し、国営事業としての大規模な灌漑事業実施は不可能となり、川辺川ダムから水を引く利水事業は白紙になりました。
4の「発電」についても、ダムの完成時期や同社の負担額が不透明であることを理由として、2007年に電源開発株式会社が川辺川ダムの発電事業からの撤退を表明しました。
2008年の知事のダム反対表明、2009年の国による中止が決まった際には、ダムの1の「洪水調節(治水)」効果の是非については言及されることなく、ダムによらない治水を検討する場において治水代替案を検討する形で引き継がれました。しかしながら、国交省は実質的には従来のダムによる治水効果に固執し、非現実的な治水代替案を提示するばかりで、ダムによらない治水対策は2020年7月に球磨川豪雨災害が起きるまでの12年間、抜本的な対策が行われることなく無為に時間だけが過ぎました。
| ■4.川辺川ダムによってどこが水没するの? |
川辺川ダムは、熊本県球磨郡相良村の北部、藤田地区に予定されています。そのため、水没地のほとんどは五木村側にあります。
水没予定地区となっているのは、川辺川沿いの相良村北部と、五木村の南部・中心地で、水没範囲は303ha、戸数は528戸です。
地図をもっと大きく
ダムによる水没地区の規模
■相良村 人口(全体数) 240名 世帯(全体数) 60世帯 面積 68.928ha(68万9,280m2) 公共施設 小学校、公会堂 地区 藤田(32世帯)、野原(28世帯) ※チッソ第二発電所(六藤)は発電所自体は水没予定地ではないが、取水口のある五木村野々脇地区が水没するため、ダムが建設されれば廃止される。
■五木村 (昭和56年4月29日補償基準日現在) 人口(全体数) 1,457名(3,356) 水没率 43.4% 世帯(全体数) 493世帯(1,019) 水没率 48.4% 面積 244.3ha(244万3000km2) 内訳:田/19ha、畑/35.9ha、山林/139.9ha、宅地/21.0ha、その他/28.5ha 公共施設 村役場、孝行、中学校、小学校(2)、森林組合、診療所、農協、消防署、保育所、駐在所、郵便局、公会堂(3)、児童館、営林署、商工会、神社、寺院、発電所(2)、県道、村道、林道、鉱区権(3)、漁業権 地区 小浜、金川(かなごう)、清楽、野々脇、大平、逆瀬川(さかせごう)、板木、下谷、三方谷、頭地(下手、田口、溝ノ口、久領)、高野、土会平(つてひら)
| ■5.現在どんな状況なの?(1966年から2023年10月まで) |
川辺川ダム計画は、1963〜1965年の3年連続水害の翌年、1966(昭和41)年に、建設省(当時)によって発表されました。治水、利水(かんがい)、発電を目的とした多目的ダムでした。
五木村では、発表直後から強い反対の声が上がりましたが、1980年代半ば以降ダム受入れへ動き、1996年には本体工事着工に同意しました。一方、1990年代半ばから、人吉市を中心にダム反対、見直しの世論が高まり始めました。その背景には、環境問題への意識の高まり、ムダな大型公共事業の見直し、ダムによる治水効果の限界について認識の広まり、利水計画策定の際の国による強引な農家の同意取得手続きが明らかになってきたこと(後の利水裁判提訴)などがあります。住民・市民の間からは、ダムによらない治水は可能とする治水代替案が提示され、費用対効果や基本高水流量に関し、国のダム計画について疑問の声が高まっていきました。
1996年からは、ダムから水を引く国営川辺川総合土地改良事業(利水事業)への参加を拒否する農家による川辺川利水訴訟が始まりました。
そのような中でも、国はダム建設の姿勢を崩さず、球磨川漁協(球磨川流域の川漁師の組合)と漁業権補償案受入交渉を始めました。球磨川漁協では激しい議論が続きましたが、ダムが漁業や河川環境に与える影響の大きさへの懸念の声が強くなり、2001年に国から提示された漁業権補償案の受入れ拒否が確定しました。国は、ダム建設予定地の漁業権や水没予定地の土地所有権の収用採決申請を行い、強制収用手続きに乗り出しました。
2001年12月からは、国の説明責任を果たすため、潮谷義子・前熊本県知事の提案により、熊本県を総合調整役に、治水と環境をテーマとした住民討論集会が始まり、2003年末までにのべ9回開催されました。これにより、ダムを巡る問題や疑問点が広く県民の間に知られるようになりました。
2003年、川辺川利水訴訟の控訴審で国(農水省)側が敗訴し、ダム利水事業が白紙になりました。ダムの目的の一つである「利水」が失われたことで、強制収用の前提であるダム基本計画の変更が否めないことから、2005年、熊本県収用委員会の勧告を受け、国はやむなく収用申請を取り下げました。
2006年に利水計画が正式に中止となり、2007年には電源開発(株)が川辺川ダムの発電事業からの撤退を決めましたが、ダム計画そのものは「塩漬け」され、そのまま生きていました。ほかにも、2004年に国交省内部文書によって明らかになったダムダム事業費増額問題や、住民討論集会での議論を通して明らかになった八代地区萩原堤防問題、球磨川漁協のダム推進派執行部による漁協をめぐる問題など、ダムをめぐるさまざまな議論は未解決のまま残されていました。
2008年、蒲島知事が就任すると、川辺川ダム問題について決断することを表明。球磨川流域の相良村長、人吉市長がダム反対表明したことを受けて、2008年9月、県はダム反対を表明。知事不同意により国はダム計画を続けることが難しい状況になり、翌2009年9月、民主党政権下だった政府は川辺川ダム中止を発表しました。
その後、国・県・流域12市町村首長は、ダムによらない治水と、水没予定地の五木村の地域振興を協議する会議を設置しました。
五木村の残された地域振興・生活再建事業(ソフト・ハード)を進めるための財源として、県は基金を作り、村ではダムを前提としない地域づくりが進みました。
一方で、「ダムによらない治水」の協議は、大きな進展のないまま停滞。一部の排水施設や堤防整備などは行われましたが、川辺川ダム建設を前提とした球磨川の治水計画の抜本的見直しや、代替治水対策の着手がされないまま12年間が過ぎました。そして2020年7月4日、球磨川豪雨災害が発生しました。
災害の検証もそこそこに、蒲島郁夫知事は2020年11月、「命と清流を守る唯一の選択肢」として、流水型での川辺川ダム計画復活を表明。これを受ける形で、国はその後川辺川ダム建設のための手続きと関連工事を急ピッチで進めています。
県知事の強い意向により、環境アセスメント法に定めるものと「同等の」環境アセスメントが実施されることになりましたが、ダムを強行に進めたい国自身による、環境庁の管轄から外れたアセスの内容は非常に恣意的で、せっかくの環境アセスが、ダム建設のための通過儀礼として抜本的な環境影響回避対策が検討されないままに進んでいるのが現状です。